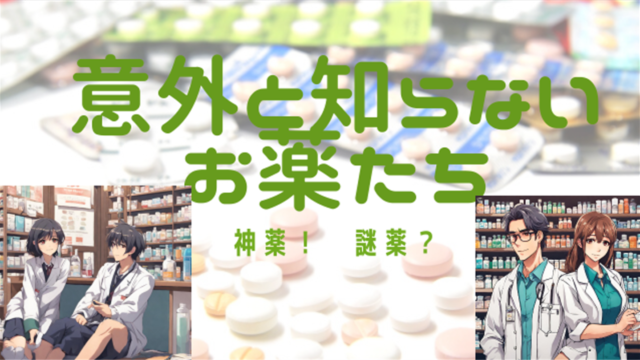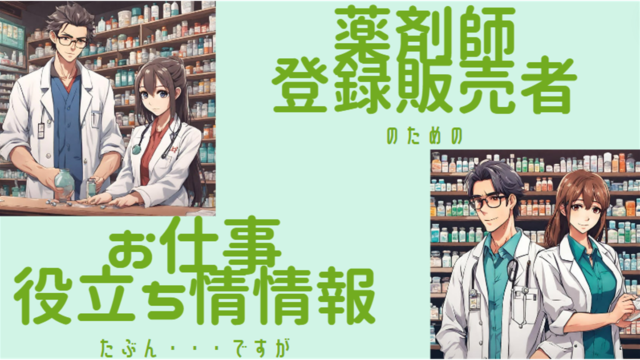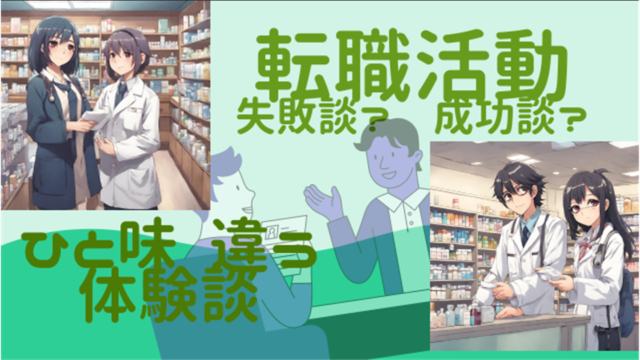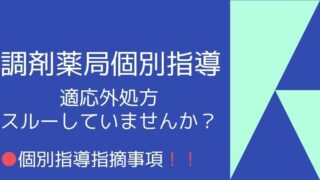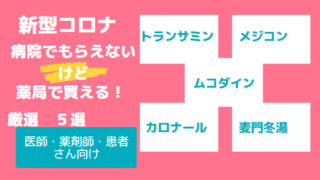こんにちは。薬剤師&ケアマネ卵&ブロガーのゆるやく
です。
諸事情あって、毎年ケアマネ勉強を忘れない程度にやっている変わり者です。
褥瘡
褥瘡のできやすい部位は、仙骨部だが、尾てい骨や肩甲骨など、仰向けで
骨が出てるところ全般にできる可能性があります
褥瘡(じょくそう)発生要因
- 患部の圧迫
- 低栄養
- 介護不足
褥瘡の対応
- 体位変換(2時間ごと)
- エアーマットなど褥瘡予防具を使用+体位変換
- 感染症防止のための入浴や清式
ただし発赤部へのマッサージは厳禁 - 高タンパク・高カロリーの栄養補給
タンパク質は、体の皮膚の原料になる栄養素です - 褥瘡の治療は医療職
真皮を超える褥瘡は、訪問看護の特別管理加算対象 - 新たな褥瘡防止のアセスメントを実施し再発防止
問題例
エアーマットを使用すれば体位変換はしなくてよい→×
発赤部の血行を良くするため、丁寧にマッサージする→×
口腔ケア
口腔の健康が体の健康を左右すると言ってもいいくらい
重要です。嚥下がうまくできないと誤嚥性肺炎のリスクもあがる
肺炎は死亡原因のトップクラスなので要注意です
嚥下の過程
- 食べ物を見る(認知期)
- かむ(準備期)
- 舌で喉へ送る(口腔期)
- 喉から食道へ(咽頭期)
- 食道から胃へ(食道期)
えんげ に じ こ い っしょ に食べよう
(嚥下に事故!! 一緒に食べよう)
【嚥下→とろみ】だけでなく
どの過程で嚥下障害が発生するか見極めアセスメントをする
噛めない人はとろみじゃなく入れ歯の治療などが必要かもしれない
不顕性誤嚥
高齢者は誤嚥に気づかず、いつのまにか誤嚥に注意
- 誤嚥を防ぐためには
液体は、とろみや半固形状のものにする - 誤嚥性肺炎を防ぐために口腔ケアが重要
口の中がばい菌だらけで、それを誤嚥して肺に入るとやばい - 口腔ケアが1回しかできない場合は、夕食後に行う
(歯を磨かないで寝た口なんて想像できないですよね・・・) - 義歯は外して口腔ケアを行い、義歯はポリデントへ
排泄の介護
排便障害は、デリケートな問題なので、自尊心に配慮
引っ掛け問題
排泄介助は自尊心に配慮し、なるべく視線を向けず手早く行う→×
褥瘡の発見などの可能性もあるので、視線はそらさず手早く実施
尿失禁は、以前やったのを復習
五木切腹です (溢流 機能 切迫 腹圧)
機能性失禁においては、排せつ動作を妨げるものがないか
アセスメントが必要
便失禁が悪化しないよう下剤の使用は注意が必要
問題例
高齢者の便失禁を予防するため、下剤の使用は控える→×
介護者が決めるのではなく、こういうのは医師の判断
最後に
この辺りは、実際に介護の現場に立っている方の方が
理解が深いと思います
そのため、教科書的な対応と、実際の対応が違っている場合は
教科書的対応がどうなのかをおさえておくことが試験対策に
必要となります
(2025/02/05 01:36:05時点 Amazon調べ-詳細)
(2025/02/05 06:10:02時点 Amazon調べ-詳細)
次へ
前へ