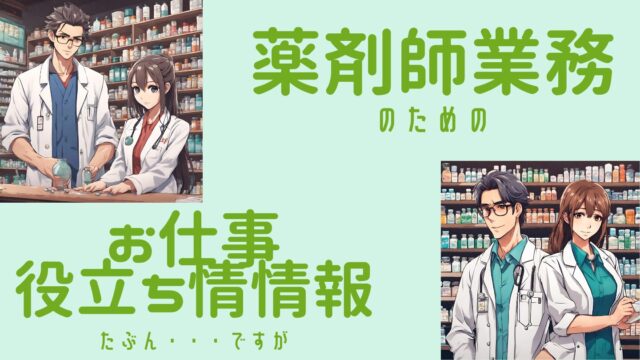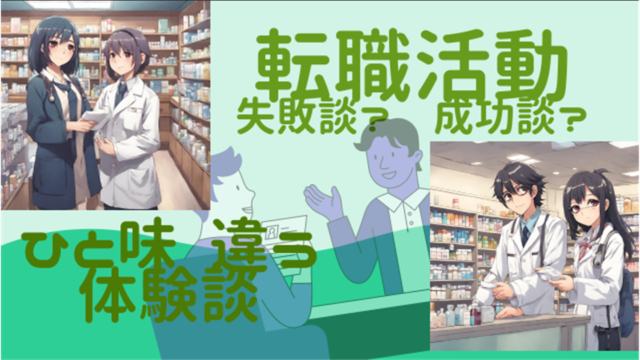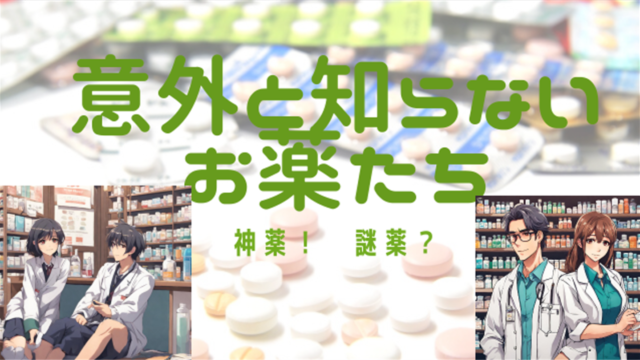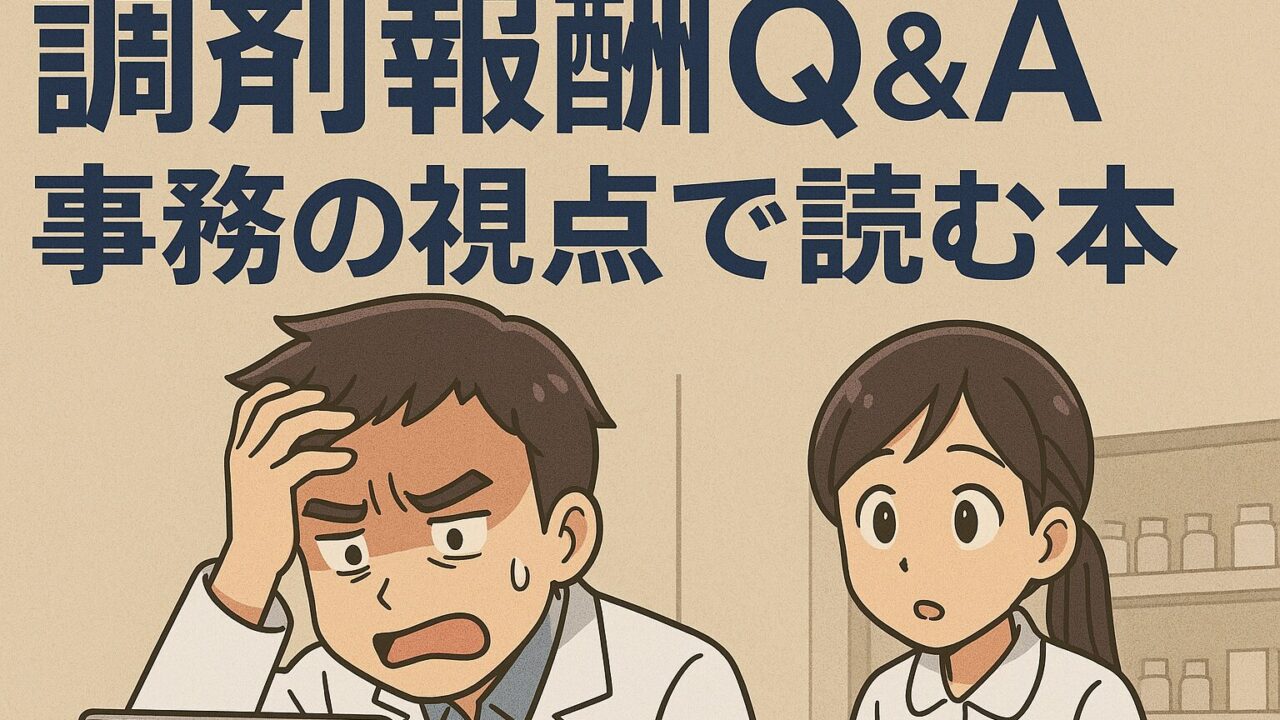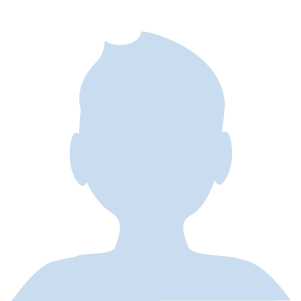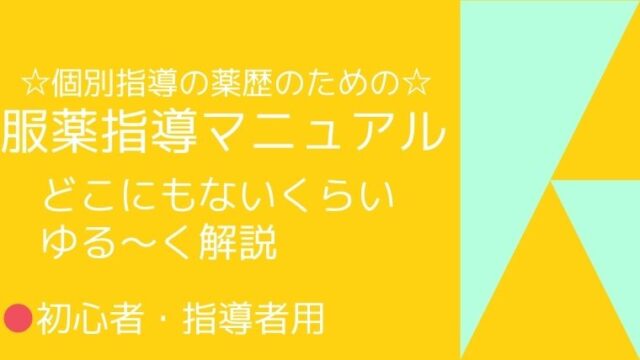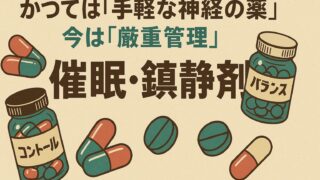- 本ページはプロモーションが含まれています
Amazonなどの商品ボタン(下記)は、販売を目的としていません。商品検索用です
もっとお得なショップがあるかもしれませんので、購入する際はサイト内でショップをご検討してからにしてください。
![]() 免責
免責
正確性に配慮しておりますが、記事の活用はご自身の責任の下でお願いいたします。
当コンテンツに起因するいかなる事項においても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
薬が減ったのに会計アップ!? 現場でヒヤリとする瞬間

調剤薬局の受付で、患者さんからこんなクレームを受けたこと、ありませんか?
たとえば、1日2回服用の薬が2種類あって1剤分だったのに、片方の薬の用法が1日1回に変更された結果、2剤に分かれて調剤料がアップしてしまったケース。
患者さんからすれば「薬が減ったはずなのにおかしいじゃないか!」と不満爆発です。
現場の私たちは「い、いや、実はこれ保険点数のマジックなんです…💦」と内心パニック。
実際には、薬の種類や量が同じでも服用タイミングの違いで調剤技術料(調剤料)が変わることがあります。
つまり保険調剤のルールによる正当な計算結果なのですが、初見の患者さんにはなかなか理解してもらえません。
こうした“あるある”トラブル、現場では日常茶飯事ですよね。
(なにこれ?という調剤料の計算方法とか詳しく知りたい方は、『保険調剤Q&A』でいろいろ解説されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね!)
レセコン入力の落とし穴:謎の返戻にドキッ

調剤報酬の計算は複雑で、レセコン(レセプトコンピューター)任せにしていても油断できません。
処方箋どおりに入力したはずなのに、出来上がったレセプトの点数がどこかおかしい…なんて経験はないでしょうか?
「まあいいか」と請求を出したら案の定、後日返戻として突き返される羽目に。
事務「えっ、どこが間違ってるの!?」と大慌て。
実は特殊な算定ルールがあったのにレセコンが拾えていなかったり、こちらの設定ミスだったりと理由は様々ですが、とにかく返戻対応は手間もストレスもかかります。
さらに怖いのは、同じような返戻を連発してしまうこと。
「またこの薬局か…ちゃんと分かってないんじゃ?」なんて厚生局に睨まれたら大変です。
頻繁に返戻や請求誤りがあると、「分かってない薬局」と疑われて個別指導にお呼び出し…なんて噂もあり、背筋が凍りますよね💧。(個別指導=行政からのご指導タイム、できれば一生ご遠慮願いたいイベントです!)
「この点数なに?」患者の質問攻撃にタジタジ…

調剤薬局の会計窓口では、患者さんから思わぬ質問が飛んでくることもあります。
たとえばお会計中に「この◯◯料って何の点数?」と調剤明細書を指差され、薬剤師さんがフリーズ…なんて場面、見たことありませんか?
ググってもわからない・・・。
普段は冷静沈着な薬剤師さんも、保険点数の細かい内訳をその場で聞かれると「えーっと、それは…💦」と焦ってしまうことがあるのです。
後ろに他の患者さんが並んでいるときなんかは、もう冷や汗タラタラの瞬間ですよね。
または、患者さんから「薬の説明はいらないから薬学管理料は取らないで」なんて直球で言われてしまうケースも。
薬剤師「いやいや、説明しなくても実はこの料金いただくことになってまして…(どう説明しよう!?)」と固まる…📖。
実は薬学管理料(服薬指導料など)は、薬剤師が安全にお薬を使ってもらうために必要と判断したら患者の申し出があっても算定してOKとルールで決まっています。
しかし患者さんからすれば「必要ないサービスなのにお金取らないでよ!」という思い。
現場では説明に本当に困りますし、下手をするとクレームに発展しかねない厄介事ですよね。
レセコン任せは危険!“根拠を自分で確認”のススメ
こうした現場の「焦り」やトラブルを経験すると痛感するのが、レセコンだけに頼る怖さです。
便利なレセコンも完璧ではなく、最終的に責任を負うのは人間である私たち。
だからこそ、請求ルールの根拠を自分で理解し、確認できる力が大切になってきます。
レセコンの計算結果が本当に正しいのか?
患者さんに聞かれたときサッと説明できるか?
そのためには、日頃から調剤報酬ルールを勉強しておく必要があります。
とはいえ、「全部覚えるなんてムリ!」というのが正直なところ…。
法令や点数表を丸暗記するのは現実的じゃありませんし、調剤報酬は改定も多く内容もコロコロ変わります。
そこで強い味方になってくれるのがQ&A形式の解説書なんです!
現場の疑問にズバリ答える救世主、『保険調剤Q&A』
『保険調剤Q&A』は、まさにそんな悩める調剤薬局事務・薬剤師のための救世主的な一冊。
調剤報酬の定番書籍で、調剤報酬改定のたびに内容がアップデートされます。
日々の薬局業務で「これどう算定するんだろう?」「この場合点数付くの?」と湧いてくる疑問について、ズバリQ&A形式で解説してくれる優れものです。
施設基準の要件から点数算定方法、特殊なケースでの扱いまで項目ごとにまとまっていて、索引から逆引き検索もできるので調べたいことがすぐ探せるのも魅力。
新人事務さんからベテラン薬剤師さんまで幅広く役立つ一冊として知られています。
現場で起こりがちな疑問に、「公式資料には載っていないけど実際どうなの?」というグレーなケースも含めて答えてくれるので、一薬局に一冊は必須と言われるほど頼りになります。
先ほどの「薬が減ったのになぜ高くなった?」といったケースや、「薬学管理料を取っていいの?」といった悩ましいシーンも、この本を開けば根拠と対処法がバッチリ書かれているんです。
まさに調剤事務にとってはお守り代わりになる心強い存在ですね。
薬剤師も持ってない!? 持ってる事務は一目置かれる
ところで、この『保険調剤Q&A』、実は薬剤師でも意外と持っていない人が多いのをご存知でしょうか?
調剤報酬のプロであるはずの薬剤師さんでも、「うちにはレセ担当の事務さんいるし…」なんて油断していたり、忙しくて勉強の時間が取れなかったりで、常に手元に置いている人ばかりではないんです。
そこへいくと、事務スタッフがこの本を持っているというのはちょっとしたギャップ効果!
「え、こんな本あるんだ。持ってるの?すごいね!」と薬剤師から一目置かれる存在になること間違いなしです😁。
実際、調剤報酬の疑問に強い事務さんは貴重な存在で、薬剤師から「◯◯さん、ここって算定できますかね?」なんて頼られる場面も出てくるかもしれません。
普段は薬剤師のサポート役が多い事務ですが、この本を活用して知識をつければむしろ薬剤師をフォローできる頼もしい相棒になれるわけです。
なんだか職場での存在感もアップして、ちょっとした優越感…?(なんて😊)
持つだけじゃもったいない!ちゃんと読んでパワーアップ
ただし!せっかく『保険調剤Q&A』を手に入れても、持っているだけでは宝の持ち腐れです。
厚めの本なので「買ったはいいけど置物状態…」なんてことにならないようにしましょう。
暇な時間にパラパラめくって日頃から内容に目を通しておくことが大事です。
全部を完璧に覚える必要はありませんが、「ああ、こんなケースでは点数こうなるのね」と知識のストックを増やしておくだけで、いざという時の対応力が格段に上がります。
具体的な算定例などは深入りしすぎず、「この本に確か書いてあったな。詳しく調べる必要が出たら確認!」くらいのスタンスでOK。
自分の中に「調剤報酬Q&Aデータベース」ができてくると、患者さんに質問されても落ち着いて説明できますし、レセプト入力時にも「ここは注意が必要だな」と先回りできるようになります。
「知識は力なり」とよく言いますが、本当にその通り!日々コツコツ読み進めておけば、いざという時に本があなたを助けてくれるでしょう。
『保険調剤Q&A』でクレーム予防&返戻対策もバッチリ!🎉
最後に、『保険調剤Q&A』を手元に置いて活用することで得られるメリットをまとめてみます。
患者クレームの予防・対応力アップ: 調剤報酬の仕組みを理解していれば、薬剤変更による負担増など起こりうる事態を事前に把握できます。
患者さんへの説明も的確にできるので、「なぜ金額が上がったの?」と聞かれても冷静に対処可能。不要なクレームを減らし、信頼関係を築けます。レセプト返戻の激減: 請求ルールを把握して入力すれば返戻や査定を食らう回数も激減します。結果として業務効率もアップし、ヒヤヒヤしながら訂正対応に追われる夜とはサヨナラできます。
薬剤師のフォロー&チーム力向上: 事務が調剤報酬に強いと、薬剤師も安心して業務に集中できます。
あなた自身が「動く調剤報酬マニュアル」のような存在になれば、患者対応でも即座にフォローでき、チーム全体のスキルアップにもつながります。
調剤薬局事務の皆さん、日々の業務で感じる「現場の焦り」を乗り越えるには、知識という武器が一番の安心材料です。
その強力な相棒として『保険調剤Q&A』を活用し、クレームにも返戻にも負けないスマートな事務を目指しましょう!
今日から早速、本棚の『保険調剤Q&A』を開いてみませんか?
きっと「あ、これウチでもあった!」という事例が見つかって、「なるほど!」と膝を打つこと請け合いです。そして明日からは、自信を持って現場に臨みましょう。👍
さあ、『保険調剤Q&A』片手に、クレーム0・返戻0を目指して楽しく頑張りましょう!
現場の困ったあるあるも、これで「大丈夫、任せて!」と笑顔で言える日が来るはずです。共に頑張る調剤事務仲間として、あなたの健闘を祈っています!🚀