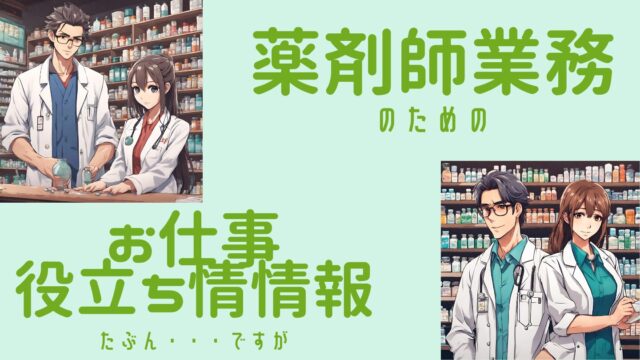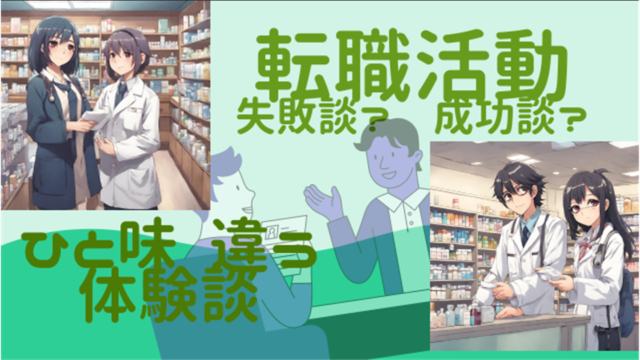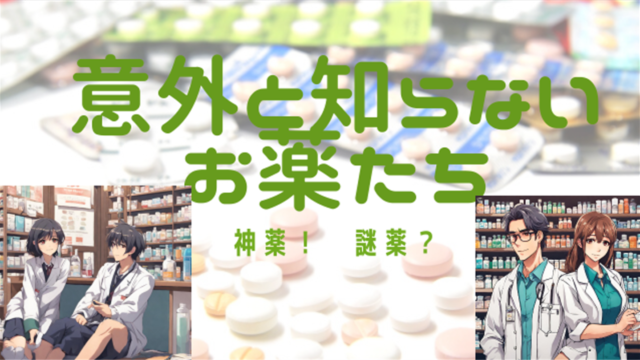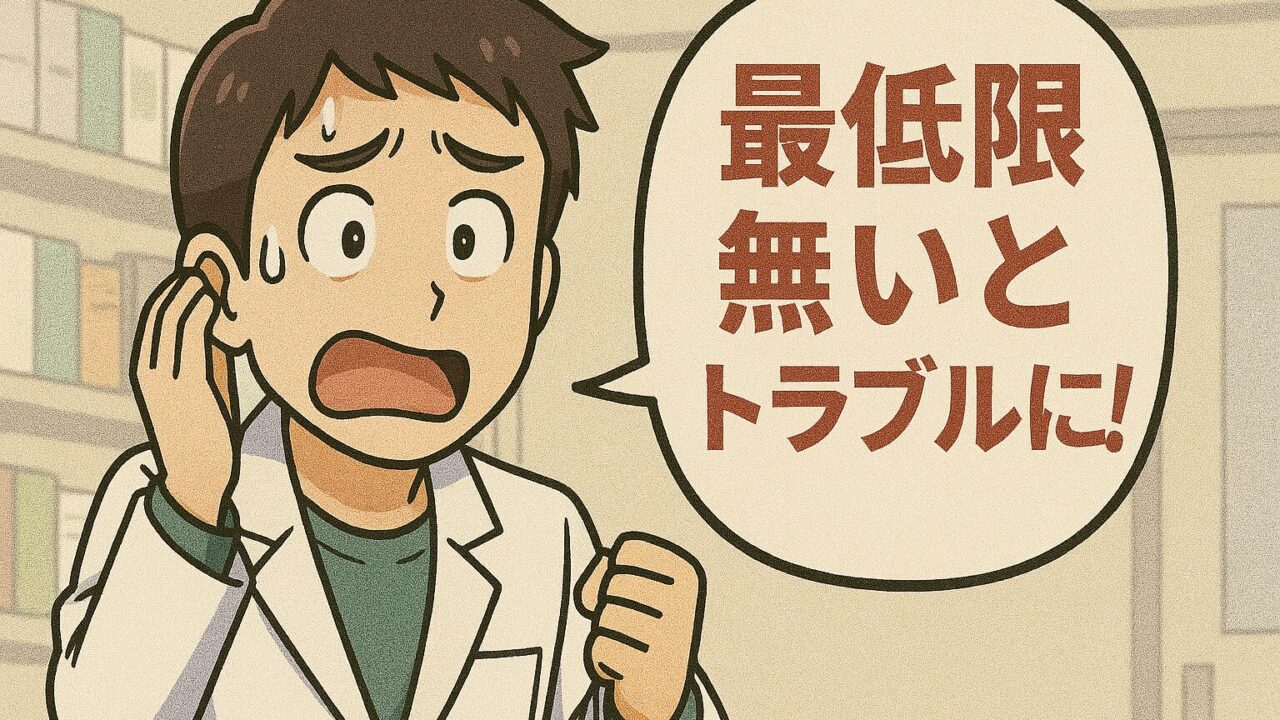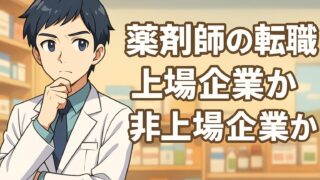- 本ページはプロモーションが含まれています
Amazonなどの商品ボタン(下記)は、販売を目的としていません。商品検索用です
もっとお得なショップがあるかもしれませんので、購入する際はサイト内でショップをご検討してからにしてください。
![]() 免責
免責
正確性に配慮しておりますが、記事の活用はご自身の責任の下でお願いいたします。
当コンテンツに起因するいかなる事項においても、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
はじめに
薬局で働く薬剤師の皆さん、今日もお疲れさまです。
「これ粉砕していいんだっけ?」「小児の薬?量とか知らんがな!」
日常業務でこんな風に思ったこと、ありませんか?
正直、ググればなんとかなるでしょ?って思ってた時期、僕にもありました。
でもね、ネットで出てくる情報って、実際にはピンポイントで役に立たないことが多いんです。
特に保険調剤とか加算のことなんて、「そんなの知らんよ」ってネットが言ってる感じ。
だからこそ、無難に乗り切るために「絶対これだけは持っておけ!」という書籍を紹介します。
安心してください。これを揃えれば、とりあえず問題が起きたときに冷静でいられるようになります。
【1. 保険調剤Q&A 最新版必須】
「保険調剤?計算?レセプト?とりあえずレセコンにお任せでやるか!」
ってやってると、そのうち厚生局から**「個別指導」のお知らせが来ますよ。
この本、ちょっと困った調剤報酬の計算から加算の算定根拠までいろいろ載ってます。
ネットで「薬学管理料 取らないでって患者から言われた場合」とか調べても、出てくるのは、
「そういうケースあるよねー」みたいな雑談記事だけ。
この本には、ちゃんと
「業務放棄に近い」とか、
「管理料取ってないから管理してません、知りませんじゃ済まされない」
とか、リアルなリスクがしっかり書かれてるんです。
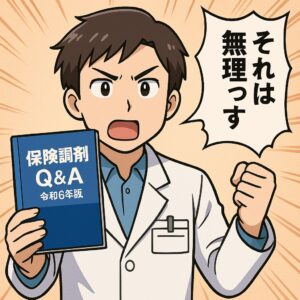
◆ こんな人におすすめ
「計算?まあ適当に…」ってやってる人
患者に「加算取らないで」と言われて「え、無理っす」って言えない人
上司に「これ、ちゃんと算定してる?」って言われて固まる人
◆ これがないとどうなる?
あのレセプトあってたかな?個別指導にビクビクする日々
患者に「なんで加算?」って言われてキョドる
慌ててネット検索→結局わからない→上司に怒られる
【2. 実践 小児薬用量ガイド】できれば最新
「子供の薬?とりあえず医師を信じとくか!」
…いや、ちょっと待って。
その「信じてそのまま出す」っていうのが一番危険なんです。
特に小児の処方箋なんて、添付文書だけじゃ用量が分からないことが多すぎ。
「いやー、まさかこの量はないでしょ…」って思って確認したら、合ってたとか普通にある。
この本なら、体重や年齢ごとに適正量がパッとわかるので、「え、これマジ?」っていう不安感を一発で解消してくれます。

◆ こんな人におすすめ
小児科の処方箋を見ると「うわぁ」と思う人
添付文書を見ても「え、結局どれ?」ってなる人
医師を信じたいけど、やっぱり確認したい人
◆ これがないとどうなる?
自己流で出して間違ってたらアウト
「まあ大丈夫でしょ!」→実際は大丈夫じゃない
医師に確認しようにも、自信がなくて電話できない
【3. 錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック】できれば最新
(2025/04/13 20:50:03時点 楽天市場調べ-詳細)
「粉砕OKって書いてないけど、ダメとも書いてないし…やってみっか!」
その思考、事故の香りがします。
特に一包化が絡むと、もうカオス。
粉砕していいのか?一包化してもOKか?
添付文書だけじゃ分からないケースが多すぎて、慌ててネットで調べても出てこない!
これ持ってると、「ちょっと怪しいかも」と思った時に即確認できるから安心。
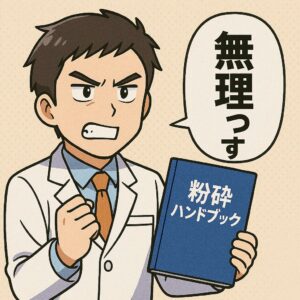
【4. 軟膏・クリーム配合変化ハンドブック】できれば最新
「軟膏とクリーム?まあ混ぜても問題ないっしょ!」
それがドロドロになったり、分離したりして、患者から「塗れないんだけど?」とクレームが来る未来が見えます。
実は混ぜたらアウトな組み合わせ、意外と多い。
添付文書には書かれてない混合可否を知るためには、この本が頼り。
「軟膏なのにドロドロクリームになった」事件を防ぐために、1冊持っとけ。
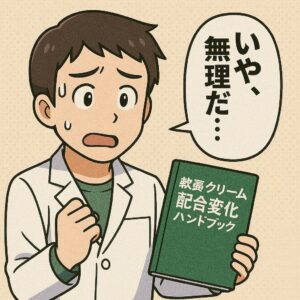
【5. 調剤指針】 最新版必須
これはまあ、どこの薬局にもあるはずですが・・・古いとダメです。
「個別指導?大丈夫っしょ!」
いやいや、最新版を持ってないと監査が厳しくなる噂もあるくらい重要な一冊。
加算や点数がよくわからないとき、ネット検索しても「改定前の古い情報」ばっかり。
辞書みたいに引けるこの本があれば、いざという時に慌てなくて済む。
「最新持ってないの?」って厚生局の人にツッコまれる前に、ちゃんと備えておこう。
【意識高い系新人へ、ちょっと言わせてくれ】
「治療薬マニュアル?今日の治療指針?薬が見えるシリーズ?おお、勉強熱心だね!それ、俺も見習いたいくらいだよ。」
「自分磨き大事だよね!」って思うんだけど、ちょっと待って。
その本、めちゃくちゃ意識高いし、医師とディスカッションする時には頼りになるよね。
でもね、それ持ってるだけで安心してない?袋詰めは下級薬剤師どもに任せておけみたいな。
現場でまず求められるのは、「調剤過誤を起こさない」「レセプトミスをしない」「似たような返戻連発して個別指導に呼ばれない」こと。
そこをクリアして初めて、「服薬指導力アップ」とか「病態理解」が活きてくるわけよ。
◆ これがわかってないとどうなる?
「小児の薬、用量これって普通?」→結局誰かに聞く
「粉砕大丈夫、これ一包化OK?」→調剤室で固まる
- 勢いで粉砕したけど、数日後患者さんのところで変になってない?とあとから不安に襲われる
「軟膏混ぜたら変な色になった」→「え、こんなはずじゃ…」
「薬学管理料?なんかやらなくてもいいって言われたし、今回サービスで取らないでおくか」→「え、その考えマジでアウトだよ」
◆ 学校じゃ教えてくれない、でも現場じゃ必須
学校で教わるのは、「薬理学」とか「治療薬の作用機序」とか、確かに大事なことばっかり。
でもね、実際に現場に出てみると、「粉砕してOKか?」とか「加算の根拠」とか、そういう実務的な問題で頭を抱えることが多いんだよ。
特に、保険調剤の仕組みなんて学校じゃほぼ教えてくれない。
でも、現場では「加算ミスで返戻になった、あとで患者さんに返金した」なんて日常茶飯事。
◆ だから、まずは最低限の備えを押さえよう
勉強して知識を高める姿勢、ほんと素晴らしい。
けど、その前に「最低限これだけは揃えておけ!」という書籍をしっかり持ってないと、結局困るのは自分なんだ。
無難に乗り切れる環境を作った上で、勉強していこう。
「俺もその姿勢、見習いたいよ!」と思うけど、まずは「最低限の安全策」を押さえようね。
さいごに
ネットで調べても出てこない実務情報をカバーするためには、今回紹介した本を持っておくのがベスト。
「無難に乗り切りたい」意識低い系薬剤師でも、「意識高く勉強したい」熱心な薬剤師でも、まずは「安全第一」でいきましょう。
「何も起きないのが一番の正解」なんだから、リスクを減らして無難に乗り切るために、まずはここから揃えてみてください。
(2025/04/13 20:50:03時点 楽天市場調べ-詳細)