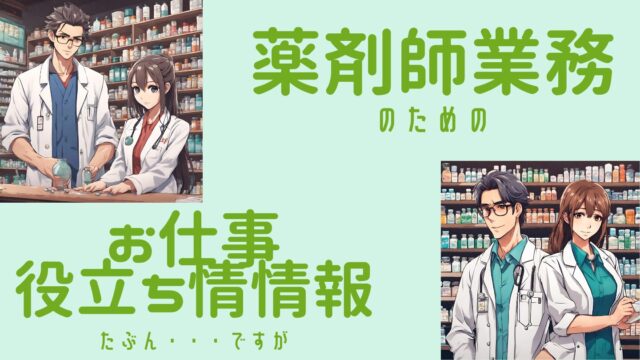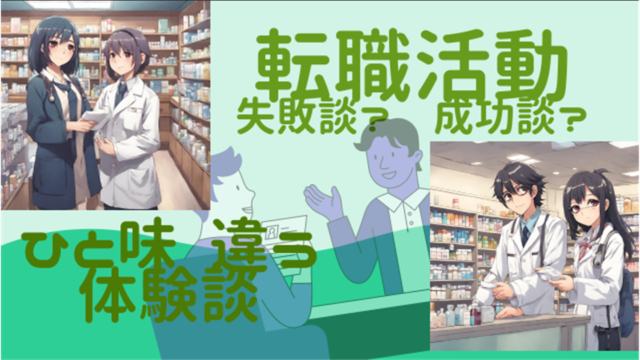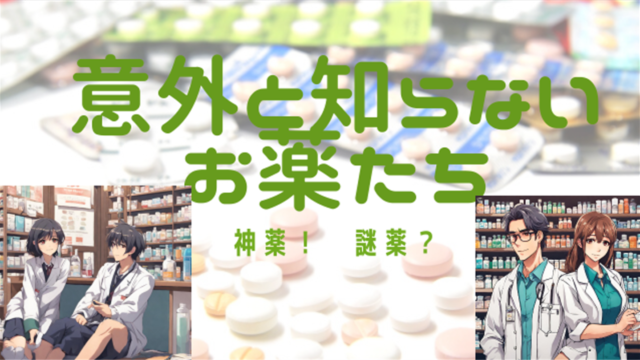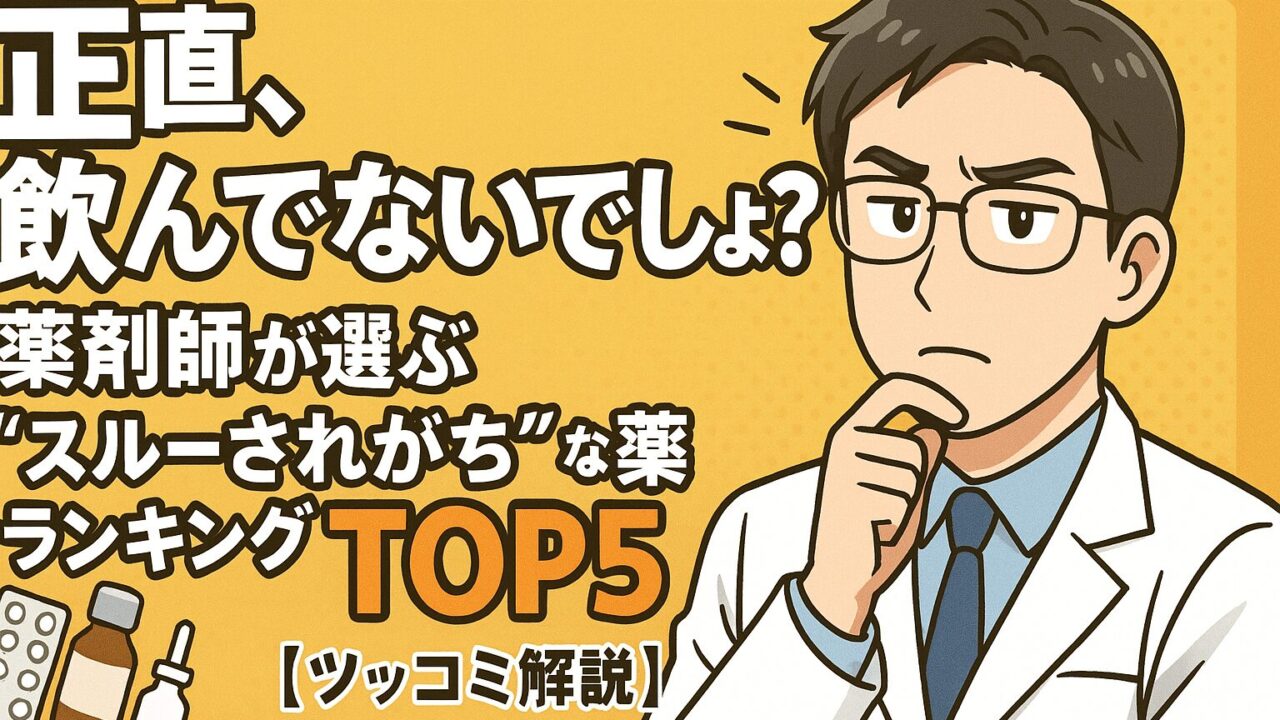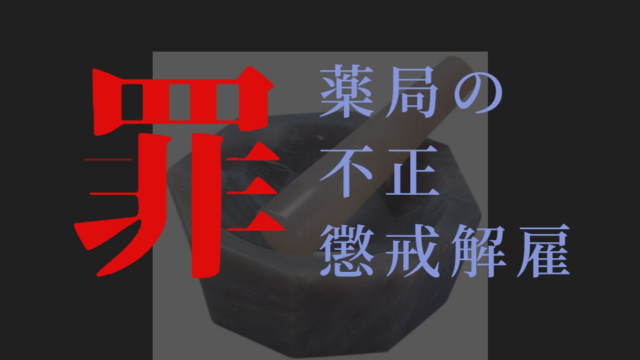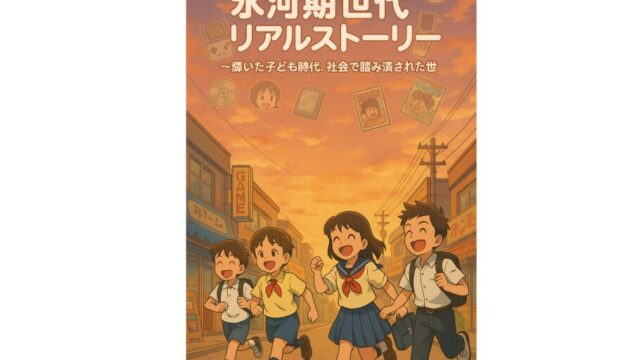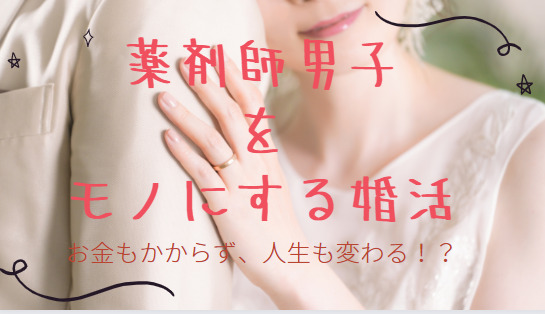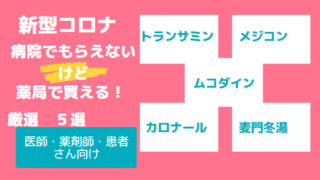・プロモーションを含みます。
薬剤師が愛とツッコミで全力解説 はじめに
「薬はきちんと飲みましょう」って言われるけどさ、
そんなの分かってる。
でもね、分かってても“続かない薬”って、あるんです。
薬剤師から見てると、飲まれてない薬ってだいたい決まってる。
しかもそれ、出す側もなんとなく気づいてたりする。
今回は、薬剤師が現場で何度も遭遇した「スルーされがちな薬たち」をランキング形式でぶっちゃけてみます。
ちょっと笑って、ちょっと共感して、こっそり思い当たったら、ぜひ続きをどうぞ。
第1位:整腸剤(ビオフェルミン・ラックビーなど)
「整腸剤って…ヨーグルトでよくない?」
→ それ、全然別物だから!
抗生物質とセットで出すことが多いけど、「おまけ感」がすごくて、だいたい雑な扱いを受けがち。
しかも納得いかないのがここ:
抗生剤は1日1回なのに、整腸剤は1日3回。なんで!?
薬剤師も説明しながら内心で思ってます:
「これ…飲むの続かないだろうな…」
でも腸内環境が乱れると、副作用でお腹がゆるくなって治療が続けられないこともあるので、ほんとは大事なんです。
お願いだから、腸のことも思い出してあげて。
第2位:1日3回の薬(抗生剤、そしてお爺ちゃん先生の粉薬)

今のライフスタイルで“昼に薬を飲む余裕がある人”って、どれだけいます?
1日目はまだ頑張る。
2日目には昼を忘れる。
3日目には「この薬、いつのだっけ?」
→ 気づけば“気持ち1日1回”コース。
特にありがちなのが、お爺ちゃん先生の1日3回粉薬。
だいたい胃薬で、苦くて、粉っぽくて、3回。
あれ、もはや根性試し。
薬剤師の本音?
と思ってたりします(小声)。
メインで出ているPPI(強力な胃薬)の添え物感満載。
でもそれ、処方権に関わるから言えないの。
だから残ってる薬があれば、疑義照会で削除を相談したり、
「この薬、ちょっと続けにくそうでした~」
と、“この薬、人気ないですよ”サインをやんわり出してるのが我々のささやかな努力です。
第3位:子どもの漢方薬(小建中湯・抑肝散など)

いや先生、さすがに気づいてますよね?
これ、子ども飲みませんって。
「ちょっと味は独特ですが…」とか言うけど、独特じゃないのよ、フル苦味なのよ。
・粉がもふもふしてる
・量が多い
・子どもが全力で拒否する
→ 最終的に“シンク下の放置薬”化する率100%。
親も「どうすれば飲んでくれるんでしょう…」と困り、薬剤師も「…いや、それはこっちが聞きたい」と心の中で呟いてる。
錠剤やドライシロップだけにしてくれたら…って、みんな思ってるよね?
第4位:頓服の痛み止め
「痛くないけど、念のためもらっておきました」
→ それ絶対、飲まないやつ!
むしろ聞きたい。
「その“念のため”薬、これまで何回飲みました?」って。
飲んだら負けなのか、ってくらい大切に温存されがち。
しかも「薬はあまり使わない方がいいんですよね?ちょっと痛いけど我慢しました」って
“使うべきときに使わない”のは本末転倒!
もうちょっと気軽に使っても大丈夫です。「ここぞ」で使うべき薬なんですから!
第5位:点鼻薬(ナゾネックス・アラミストなど)
「これ、鼻に入ってるんですかね…?」の常連。
・シュッとしても手応えがない
・出てるのか出てないのか分からない
・使ってるつもりが実は使えてない
→ “最後まで使いきれない薬”界のエース。
しかも処方時の医師のトーンが「点鼻薬も出しておくから」という感じですでに弱い。
「一応出しときますね~」って…いや、
そりゃ患者も「重要度低そう」って感じますよ…。
でも、薬剤師として声を大にして言いたい:
点鼻薬、ちゃんと使えばマジで楽になります。
特に花粉症の時期なんて、これがあるかないかで日常生活の快適さがまるで違う。
「なんかスースーしない」とか「効いてるか分からない」って言うけど、点鼻薬って、“効いてるときほど存在を忘れる”タイプの名脇役。
説明のときは毎回熱が入ります。
「これちゃんと使ってくれたら、今年の春、だいぶ変わりますよ!」って。
使い方さえマスターできれば、人生変わる薬なんです。
だからお願い、せめて5日間は続けて使ってみて。頼む。
◆ 飲まれない薬の共通点
効果が体感しづらい
飲み方・使い方が面倒
飲まなくてもとりあえず何とかなりそう
医師も薬剤師も「うすうす分かってるけど言えない」
◆ 実はバレてます
「一応飲んでます」
「効かなかったんで、次は出してもらってません」
→ はい、それたぶんちゃんと使ってないやつ。
開封感ゼロの薬袋、余り具合、話の内容…
薬剤師は静かに全部察しています。
でも責めない。怒らない。
薬を“飲み続けたくなるようにする”のも、薬剤師の役目だから。
◆ 飲ませる力も、薬剤師の仕事です
薬を出すだけじゃダメな時代。
続けてもらってナンボです。
飲まれない理由は、患者がズボラだからじゃない。
薬が“続けにくい”仕様になってるだけ。
だから薬剤師は今日も、
「これ、飲みやすくできないかな?」
「もっと響く説明ないかな?」
と、処方された薬を“使ってもらう工夫”を探し続けています。
あなたの薬、まだ残ってませんか?
そして薬剤師は今日も考えます。
「もっと飲みやすくできないか?」
「伝え方を変えれば、続けてもらえるか?」
その一歩一歩が、信頼と服薬継続につながります。